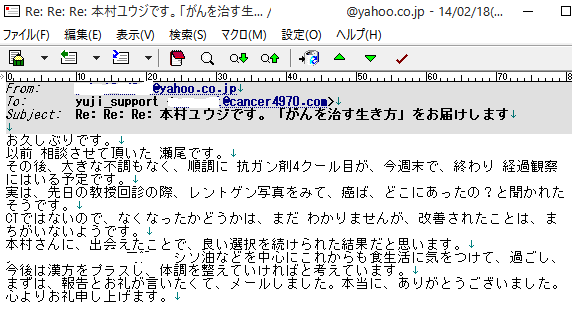肺がん手術ができる条件の基本的な考え方
肺がんの手術は、がん細胞が確認された部分やがんが強く疑われる部位をすべて切り取ることが目的です。これは局所的な治療法であり、がんのある部分とその近い組織だけを対象として行われます。
2025年現在、肺がん手術の適応条件は、がんの進行度(ステージ)と患者さんの身体の状態の両方を総合的に評価して決定されます。手術をするかどうかは、肺がんの状態(組織型、がんの進行度等)と患者さんの身体の状態(全身状態、心肺機能、年齢、他の病気の有無等)で決まります。
肺がん手術は、肉眼で確認できるがん細胞のすべてを取り除くことにより、根治を目的とした治療です。しかし、すべての肺がん患者さんが手術の対象となるわけではありません。
肺がん手術の基本的な適応条件
肺がんで手術ができる基本的な条件は以下の通りです。
がんの局在に関する条件
第一の条件は、がん細胞が片側の胸にしか存在しないことです。これは、手術によって根治的にがんを取り除くことができる範囲にがんが限定されている必要があるためです。
第二の条件は、リンパ節に転移していても、その範囲が肺のごく近くまでであることです。具体的には、同側肺内リンパ節転移や同側縦隔リンパ節転移までが手術の適応範囲とされています。
ステージ(病期)による手術適応
肺がんのステージ別にみると、非小細胞肺がんではⅠ(ⅠA・ⅠB)・Ⅱ(ⅡA・ⅡB)・ⅢA期の一部、小細胞肺がんでは限局型I-ⅡA期の患者さんが手術の対象となり、ステージによって手術法が異なります。
| 肺がんの種類 | 手術適応ステージ | 手術方法 |
|---|---|---|
| 非小細胞肺がん | I期(IA・IB) | 肺葉切除術または縮小手術+リンパ節郭清 |
| 非小細胞肺がん | II期(IIA・IIB) | 肺葉切除術または肺全摘術+リンパ節郭清 |
| 非小細胞肺がん | IIIA期の一部 | 肺葉切除術または肺全摘術+リンパ節郭清 |
| 小細胞肺がん | 限局型I-IIA期 | 肺葉切除術または肺全摘術+リンパ節郭清 |
通常、IV期(ステージ4)と診断された肺がん患者さんの場合には、手術を行うことはありません。IV期の状態では、他の臓器に肺がんが転移しているため治療の主体は薬物治療となります。
患者さんの身体的条件による手術適応
全身状態の評価
手術が可能かどうかを判断する際に重要なのは、患者さんの全身状態です。これは、がん細胞が手術で取り除ける範囲にのみあるかという条件に加えて、全身状態、年齢、合併する他の病気等から判断して、身体が手術に耐えられるのかという観点から評価されます。
患者さんの全身の状態(どのくらい元気か)を測る指標が、ECOGのパフォーマンスステータス(PS)です。一般的に、がんの完治を目指して積極的な治療を行う場合には、ECOGのパフォーマンスステータスで0~2の範囲に入っている必要があるといわれています。
心肺機能の評価
肺がんの手術では、肺の一部または全部を切除するため、残った肺で十分な呼吸機能を維持できるかどうかが重要です。呼吸機能が低下していて手術後の生活に必要な呼吸機能の回復が見込めない場合は、手術の適応から外れることがあります。
具体的には、以下の検査が行われます。
- 呼吸機能検査(肺活量などを詳しく調べる検査)
- 負荷心電図検査
- 心臓超音波検査
- 血液検査
手術予定患者さんの身体の状態は手術リスクに大きな影響を与え、特に心臓と肺の能力(心肺機能といいます)は重要です。
年齢による考慮事項
年齢だけで手術ができないということはありません。手術を行うかどうかは年齢だけでなく、心肺機能や採血所見を総合的に判断し決定されます。すなわち高齢というだけで手術ができないということはありません。普段元気で自立している高齢者は、他の患者さと同じ治療を受けることも可能でしょう。
2010年度の調査では、肺がん手術を受ける患者さんの平均年齢は68.3歳となっており、80歳を超える患者さんの割合は10.5%となっています。肺がん手術を受ける患者さんの10人に一人は80歳を超える患者さんが占めており、この割合は増加傾向にあります。
手術ができない場合の具体的な理由
以下のような場合は、手術の適応から外れることが多くなります。
身体的な理由
- 手術や麻酔に耐えられる体力がない
- 呼吸機能が低下していて手術後の生活に必要な呼吸機能の回復が見込めない
- 他の病気により重い合併症が起こる危険性がある
- 心血管系のリスク(特に動脈硬化性心臓血管障害)が高い
がんの状態による理由
- 手術できない場所にがんがある
- がんが広範囲に転移している
- 遠隔転移(他の臓器への転移)がある
- 両側の肺にがんが存在する
特殊な症例での手術適応
パンコースト腫瘍(肺尖部胸壁浸潤がん)
パンコースト腫瘍は、肺の上部(肺尖部)に発生する特殊な非小細胞肺がんです。この腫瘍は胸壁や神経に浸潤することが多く、肩から腕にかけての強い痛みを引き起こします。
パンコースト腫瘍においては多くの場合、手術前の放射線化学療法が行われています。日本臨床腫瘍研究グループが主導して実施した臨床試験の結果、肺尖部胸壁浸潤がん(パンコースト腫瘍)に対しては放射線化学療法後に手術を行うことで、よりよい治療成績が得られると考えられています。
胸壁浸潤型肺がん
胸壁(肋骨)への浸潤が見られる場合でも、限定的な浸潤であれば手術の適応となることがあります。この場合も、手術前に放射線治療と薬物療法を組み合わせた放射線化学療法が実施されることが多くなっています。
2025年最新の治療ガイドライン変更点
2025年に更新された肺癌診療ガイドラインでは、以下のような変更点があります。
小細胞肺がんの治療方針
小細胞肺がんは非小細胞肺がんに比べ、がんの進行が速く、比較的放射線治療や薬物療法が効きやすい特徴があります。そのため、標準治療として外科手術が選択されるのは限局型でリンパ節への転移がないⅠ期・ⅡA期のみに限られます。
遺伝子検査の重要性
2025年現在、一部のがんでは、遺伝子の変化に対応した薬による治療が行われているため、がんの遺伝子を調べることがあります。非小細胞肺がんでは、EGFR遺伝子、ALK遺伝子、ROS1遺伝子、BRAF遺伝子、MET遺伝子、RET遺伝子、NTRK遺伝子、KRAS遺伝子、HER2遺伝子に異常がある場合などに、対応する薬物療法を検討します。
手術前の詳細な検査と評価
手術の適応があるかどうかは、CTなどの様々な検査を行って調べます。具体的には以下のような検査が実施されます。
画像検査
- 胸部CT検査:がんの大きさや位置、周囲への浸潤の程度を詳しく評価
- PET-CT検査:がんの活動性や転移の有無を確認
- 脳MRI検査:脳転移の有無を確認
- 骨シンチグラフィ:骨転移の有無を確認
機能検査
- 呼吸機能検査:肺活量や1秒量などを測定
- 心電図・心エコー検査:心機能の評価
- 血液検査:肝機能、腎機能、栄養状態の評価
- 動脈血ガス分析:血液中の酸素・二酸化炭素濃度の測定
手術の種類と選択基準
肺がんの手術には、がんの進行度や位置に応じて以下のような術式があります。
IA期の手術
IA期では、肺葉切除術または肺葉の一部を切除する縮小手術を行い、同時に、周囲のリンパ節を一緒に摘出するリンパ節郭清も行います。
肺がんの標準手術は肺葉切除ですが、高齢者の場合には縮小手術(区域切除や楔状切除(部分切除)が選択される場合もあります。肺がん手術の根治性を保ちつつ、手術後の肺活量や体力の低下を最小限にとどめることが必要な場合は治療方針についてよく相談のうえ術式を決定することが重要です。
IB・II・IIIA期の一部の手術
これらのステージでは、肺葉切除術または片肺のすべてを切除する肺全摘術を行い、同時に、周囲のリンパ節を一緒に摘出するリンパ節郭清も行います。手術後に再発予防のための抗がん剤治療を行うことがあります。
手術以外の治療選択肢
手術ができない場合でも、以下のような治療選択肢があります。
放射線治療
病期(ステージ)別にみると、Ⅰ~Ⅱ期(ステージ1~2)では手術が標準治療です。患者さんの身体が手術に耐えられないと判断される場合や、患者さん自身の希望によっては手術ではなく、放射線治療が行われる場合もあります。
化学放射線療法
Ⅲ期(ステージ3)では多くの場合、薬物療法と放射線治療を組み合わせる化学放射線療法が行われますが、手術が行われる場合もあります。
薬物療法
Ⅳ期(ステージ4)では薬物療法と緩和ケアが標準治療となります。Ⅰ~Ⅲ期の患者さんも再発のがんに対してはⅣ期と同じ治療が行われることが一般的です。
手術リスクの評価と冠危険因子
肺がん手術を実施するにあたり、そのリスク評価として肺切除術の手術に関連する合併症や手術死、手術から時間を経た時期の身体機能を十分に考えておく必要があります。
特に注目されているのは冠危険因子です。これは、狭心症や急性心筋梗塞といった冠動脈疾患を引き起こすリスク因子のことです。具体的には以下の5つの因子に注目されています。
- 喫煙
- 糖尿病
- 脂質異常症
- 高血圧
- 狭心症などの家族歴
これら5因子のうち3因子以上を持つ方は負荷心電図検査で異常の見られる可能性が高いことがわかっています。
集学的治療の重要性
2025年現在、肺がんの治療において「集学的治療」の重要性が高まっています。これは、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた治療法のことです。
「集学的治療」の実践においては外科医のみならず、放射線治療専門医、腫瘍内科医(薬物療法の専門医)との密な連携が必要です。とりわけ、肺尖部胸壁浸潤がん(パンコースト腫瘍)などの局所進行肺がんの治療において、「集学的治療」が治療成績を改善しています。
患者さんへのアドバイス
肺がんの手術適応について理解していただくために、以下の点が重要です。
十分な相談の重要性
手術の適応は、がんの状態だけでなく、患者さん個人の身体状況や価値観によっても左右されます。担当医と十分に相談し、納得のいく治療選択をすることが大切です。
セカンドオピニオンの活用
手術の適応について疑問がある場合は、他の医療機関でのセカンドオピニオンを求めることも重要な選択肢です。
準備の重要性
手術が決定した場合は、術前の体調管理が重要です。禁煙、適度な運動、栄養状態の改善などにより、手術成績の向上が期待できます。
まとめ
2025年現在、肺がんの手術適応は、がんの進行度(ステージ)と患者さんの全身状態を総合的に評価して決定されます。基本的には、非小細胞肺がんではI期からIIIA期の一部、小細胞肺がんでは限局型I-IIA期が手術の対象となります。
ただし、病期分類では早期でも、肺の機能や全身状態が低下している場合は、手術が行えない場合もあります。一方で、年齢だけを理由に手術を諦める必要はなく、総合的な評価に基づいて判断されます。
パンコースト腫瘍や胸壁浸潤型などの特殊な症例でも、適切な集学的治療により手術の適応となる場合があります。