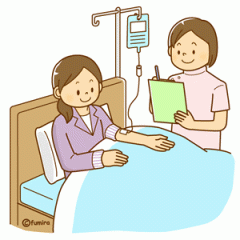
子宮がん(子宮頸がん、子宮体がん)が発見されたあと、がんの広がりを診る検査としては、内診、直腸診、経膣超音波検査、CT検査(コンピュータ断層撮影)、MRI検査などがあります。
子宮内と子宮周辺へのがんの広がりの検査
現在、最も広く用いられているのはMRI(エムアールアイ)検査です。MRI検査は、肺や肝臓など遠隔臓器への転移の有無、リンパ節転移の診断、周囲臓器への浸潤(しんじゅん)の程度の診断に有効です。
子宮の検査においては骨盤を横断面や縦断面や斜め断面などで撮影します。子宮の断面(子宮の縦断面)像で、子宮頸がんの大きさを測定したり、子宮頸部筋層浸潤の程度、膀胱や直腸への浸潤の有無を診断したりします。また、子宮頸部の横断面像から、子宮頸部側方へのがんの広がりの有無を診断します。
子宮頸がんの「病期(ステージ)分類」は、手術前に視診(膣鏡診)、内診、直腸診などにより診断します。例えば、病巣が4cmより大きければ、進行期はIb2期になり、4cmより小さければIb1期になるので、MRI検査の結果を参考にします。
MRI検査で子宮周囲への浸潤が疑われる場合は、直腸診などで浸潤がないと判断すれば、MRI検査よりも直腸診による診断を優先して、進行期はIb期とします(子宮周囲への浸潤があればⅡb期です)。
子宮体がんの場合は、がんの大きさと子宮体部筋層浸潤の程度により、後腹膜リンパ節郭清を実施するかどうかか、また、その郭清(かくせい。切除すること)範囲を拡大するかなどが変わりますので、術前のMRI検査は必須とされています。
ステージの判断としては、がんが子宮壁(筋層)に浸潤していないか、わずかの浸潤で2分の1までにとどまると評価すれば、進行期はIA期、2分の1を超える浸潤があればIB期とします。
筋層浸潤が浅くても、病巣のサイズが2cmを超えれば骨盤リンパ節郭清することが提案されますが、2cmより小さくて、患者がその意義や副作用(足のリンパ浮腫など)を理解したうえで、骨盤リンパ節郭清を希望しなければ行わないことも多くなりました。
子宮外への進展、遠隔転移の有無の検査
子宮外への進展、遠隔転移の有無を確認する検査として、骨盤と上腹部のCT検査を行います。CT検査は横断面像をみぞおちから恥骨下端まで、1cm間隔で撮像していきます。また、造影剤を用いて、解像力を上げてがんの転移か否かの診断をする場合もあります。
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
子宮頸がんの場合
子宮頸がんの場合は、骨盤リンパ節への転移(通常10mm径を超えると陽性、つまり転移の疑い)にとどまれば進行期は修正されませんが、大動脈周囲のリンパ節転移が10mm以上に達していれば、遠隔転移陽性(Ⅳb期)と評価されます。肝臓、骨などへの転移もⅣb期です。
また、CT検査では、造影剤を用いているので、腎臓の状態(尿の排泄能力)もわかります。尿管の圧迫のため、尿の流れが悪くなっていれば、その部位から上の尿管や腎盂(腎臓からの尿が集まる所)が膨らむことになります。その場合は水尿管症、水腎症と診断されます。
子宮体がんの場合
子宮体がんの場合は、骨盤でも大動脈周囲でもリンパ節転移があれば(10mm径を超えると陽性)ⅢC期であり、骨盤を越える部位への播種や転移はⅣ期です。
CT検査での診断はあくまでも疑い(疑診といいます)であり、子宮体がんの進行期診断は、手術時の肉眼的所見や病理検査で確定します。
※PET-CTについて(陽電子放出断層装置)
PET-CTは、PETとCTが一体型となったもので、従来のPETより、病巣の発見・診断能力をより高めたシステムとして注目されています。
PETによる生体の機能画像とCTによる形態画像を重ね合わせた鮮明な画像を一度で撮影できるため、がんの位置の特定や正確な診断を速やかに行うことができます。
アメリカでは、PETが普及し、術前検査で盛んに用いられています。日本でもPET-CTが徐々に術前検査に組み込まれるようになってきましたが、通常の早期がんでは、コストパーフォーマンスが悪く(支払う費用よりも価値が低い)、医療資源の適正使用の観点から問題があります。
現状では、手術や放射線治療などの局所治療をすぐにできない進行がんと診断されたとき、全身的化学療法を先行させるかどうかを判断する場合などに行われます。
以上、子宮がんの検査に関する解説でした。



