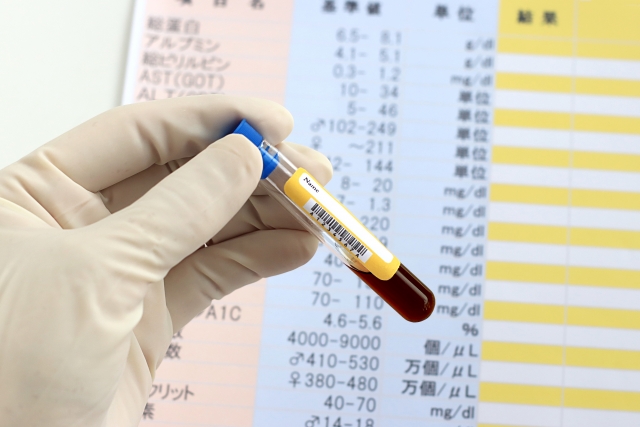
がんのバイオプシーと病理検査に革命をもたらすリキッドバイオプシーとは
リキッドバイオプシーは、血液や体液を使って行う新しい生検・病理検査の方法です。従来のバイオプシー(生検)は、針や手術で組織を採取して病理検査を行う必要がありましたが、リキッドバイオプシーは血液を採取するだけで、がんの遺伝子異常や診断に必要な情報を得ることができます。
がんの患者さんの血液には、腫瘍由来のDNA(circulating tumor DNA:ctDNA)や循環腫瘍細胞(CTC)が存在します。これらのバイオマーカーを分析することで、従来の組織生検では困難だった診断や治療選択が可能になります。
リキッドバイオプシーの検査技術と精度
主な検査対象となるバイオマーカー
リキッドバイオプシーで分析される主要なバイオマーカーには以下があります:
| バイオマーカー | 特徴 | 検査目的 |
|---|---|---|
| 循環腫瘍DNA(ctDNA) | がん細胞から血液中に遊離したDNA | 遺伝子変異の検出、薬剤選択 |
| 循環腫瘍細胞(CTC) | 血液中を循環しているがん細胞 | 転移の予測、治療効果判定 |
| マイクロRNA(miRNA) | がん関連の小分子RNA | 早期診断、予後予測 |
| エクソソーム | 細胞が分泌する小胞 | がんの転移能力評価 |
検査の精度と技術的課題
リキッドバイオプシーの診断精度は検査方法や対象とするがんの種類によって異なります。現在の技術では、特異度(正常な人を正しく判定する能力)は比較的高い一方で、感度(がんを正しく検出する能力)には課題があります。
ctDNA検査では、比較的高い感度を持ち、非常に小さな量のがんDNAでも検出できる場合がありますが、DNA量が少ない患者さんの場合、遺伝子異常の評価が困難なことがあります。また、血液細胞由来のcfDNAと腫瘍由来のctDNAの正確な区別は現在の技術では困難な面もあります。
このため、現在のリキッドバイオプシーでは偽陰性(本当は体内にがんが存在するのに、検査結果は陰性と出てしまう)の可能性があることに注意が必要です。技術改良により検出精度は向上していますが、これらの限界を理解して利用することが重要です。
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
FDA承認検査と実用化の現状
主要な承認済み検査
2020年以降、アメリカ食品医薬品局(FDA)は複数の包括的リキッドバイオプシー検査を承認しており、これらは日本でも利用可能です。
Guardant360 CDxは60以上の遺伝子の変化を検出でき、特に非小細胞肺がんにおけるEGFR遺伝子変異の検出でコンパニオン診断薬として承認されています。一方、FoundationOne Liquid CDxは300以上の遺伝子変異や改変を同定でき、マイクロサテライト不安定性や血液腫瘍変異負荷なども測定できます。
2024年には、FDAは初のがんスクリーニング用リキッドバイオプシー検査であるShieldを承認しました。これは平均的リスクの成人において、血液中のctDNAを検出することで大腸がんをスクリーニングする検査です。
日本での実用化と保険適用
日本では、標準治療が終わった、あるいは標準治療がないステージ4の固形がんの患者さんを対象としたがん遺伝子パネル検査の一部として、リキッドバイオプシーが保険適用されています。
国立がん研究センターが中心となって実施している「SCRUM-Japan」プロジェクトでは、リキッドバイオプシーを用いた場合の登録から結果返却までの期間は平均11日で、腫瘍組織の検体を用いた場合(平均33日)の3分の1となっています。
リキッドバイオプシーの臨床応用
治療選択における活用
リキッドバイオプシーは、個別化医療の実現において重要な役割を果たしています。例えば、HER2陽性大腸がんの患者さんを対象とした治験では、リキッドバイオプシーまたは組織を用いた検査でHER2陽性が確認された患者さんに抗HER2薬のペルツズマブとトラスツズマブの併用療法を実施し、約3割の患者さんの腫瘍が縮小しました。
この結果を受けて、2022年3月には化学療法の治療歴のあるHER2陽性大腸がんに対してこの併用療法の適応が拡大され、保険診療で使用できるようになりました。
治療効果のモニタリング
リキッドバイオプシーは治療の効果判定にも活用されています。CIRCULATE-Japan GALAXYの研究では、手術後にctDNAが見つかった大腸がん患者さんでも、術後補助化学療法を受けてctDNAが消えた場合は、再発する可能性が下がることが明らかになりました。
このように、リキッドバイオプシーは治療の選択だけでなく、治療効果の確認や再発リスクの評価にも有用な情報を提供します。
早期発見への応用と可能性
がんスクリーニングとしての将来性
リキッドバイオプシーの最も期待される応用分野の一つが、がんの早期発見です。現在日本で推奨されているがん検診は、乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん、肺がんの5つですが、日本人のがんによる死亡の少なくとも50%以上は検診対象外のがんが原因です。
特に膵がんや卵巣がんなど、発見された段階で手術ができないほど進行している場合が多いがんの早期発見が、血液を用いたリキッドバイオプシーによって可能になれば、がんが治る患者さんが増えることが期待されます。
多がん種早期発見検査の開発
英国や米国では、健康な人を対象としたリキッドバイオプシーによるがんの早期発見を目的とした大規模な臨床試験が実施されています。日本でも、日本人やアジア人のがんの早期発見が可能なリキッドバイオプシーの開発に向けた臨床試験の準備が進められています。
これらの検査は、将来的に人間ドックや医療機関において、少量の血液や尿の検体を解析することで、様々ながんを早期に発見することを目指しています。
リキッドバイオプシーの限界と課題
技術的限界
リキッドバイオプシーには重要な限界があります。最も大きな課題は、がんの種類によって腫瘍由来のDNAが血液中に遊離しにくいものがあることです。例えば、脳腫瘍由来のDNAは血液中に遊離しにくく、検出が困難な場合があります。
また、早期がんでは循環しているctDNAの量が非常に少ないため、検出感度に限界があります。このため、陰性結果が出ても完全にがんを否定することはできません。
偽陽性・偽陰性の問題
リキッドバイオプシーで異常が見つかった場合、体のどこにがんが存在するか確認できないことも課題の一つです。異常が見つかった場合は、他の検査で場所を探すことが必要になります。見つからなかった場合、本当にがんがあるかどうかもわからない不安な状態が長期間続く可能性があります。
炎症や組織損傷などの他の因子によって偽陽性が生じる可能性もあり、検査結果の解釈には注意深い判断が必要です。
世界市場の成長と技術革新
市場規模の拡大
リキッドバイオプシーの世界市場は急速に拡大しています。2024年の市場規模は約118億5,000万米ドルと推定され、2030年までに228億8,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率は11.5%となっています。
この成長は、がんの有病率の増加、がん診断技術の進歩、低侵襲がん診断法への需要の高まりなどの要因によるものです。北米が市場の51.15%を占めており、技術別では次世代シーケンシング(NGS)が76.17%のシェアを持っています。
技術革新の方向性
2025年以降、リキッドバイオプシー技術はさらなる革新が期待されています。検出感度と特異度の向上、解析可能な遺伝子数の増加、検査時間の短縮などが主要な技術開発の方向性です。
また、人工知能(AI)技術との統合により、検査結果の解釈精度向上や、複数のバイオマーカーを組み合わせた包括的な解析が可能になると期待されています。
今後の展望と課題
規制環境の整備
リキッドバイオプシーの普及には、規制環境の整備が重要です。FDAやEMAなどの規制機関は、リキッドバイオプシー検査に多くの臨床的裏付けを必要とするため、承認プロセスには時間がかかります。しかし、2024年にはいくつかのctDNAベースアッセイに対してブレークスルーデバイス指定や適応拡大の承認が行われており、規制環境は徐々に整備されています。
医療現場での標準化
リキッドバイオプシーが真に臨床に貢献するためには、検査の標準化、品質管理システムの確立、医療従事者の教育が必要です。また、検査結果の解釈ガイドラインの策定や、他の診断法との適切な使い分けに関する指針の確立も重要な課題です。
健康保険制度への統合
リキッドバイオプシーの普及には、健康保険制度への統合が不可欠です。現在、一部の検査は保険適用されていますが、早期発見を目的とした検査の多くは自費診療となっています。費用対効果の検証と、適切な保険適用範囲の設定が今後の重要な課題となります。
患者さんにとってのメリットとデメリット
主なメリット
リキッドバイオプシーは患者さんにとって多くのメリットがあります。最も重要なのは、血液採取だけで検査ができるため、患者さんの体への負担が少ないことです。従来の組織生検に比べて、侵襲性が低く、繰り返し検査が可能です。
また、検査結果が得られるまでの時間が短く、迅速な治療開始が可能になります。腫瘍全体の遺伝子変化を反映するため、組織生検では見逃される可能性のある遺伝子変異も検出できる可能性があります。
注意すべき点
一方で、リキッドバイオプシーにはいくつかの注意点があります。検査精度に限界があり、特に早期がんでは見落とされる可能性があります。また、異常が見つかっても、がんの存在場所が特定できないため、追加検査が必要になる場合があります。
検査費用も考慮すべき点です。保険適用外の検査では、高額な費用がかかる場合があります。検査を受ける前に、医師と十分相談し、検査の目的、限界、費用について理解することが重要です。
結論
リキッドバイオプシーは、がんの診断と治療において革新的な技術として急速に発展しています。血液を用いた非侵襲的な検査により、従来の生検・病理検査では困難だった診断や治療選択が可能になり、患者さんの負担軽減と治療成績の向上に貢献しています。
現在、治療選択や効果判定においては実用段階に入っており、早期発見分野でも有望な結果が得られています。しかし、技術的限界や偽陰性・偽陽性の問題、検査費用など、解決すべき課題も残されています。
今後、技術革新により検査精度の向上が期待される一方で、適切な利用方法の確立、規制環境の整備、医療現場での標準化が重要な課題となります。患者さんにとって、リキッドバイオプシーは有用な検査オプションの一つですが、その特性と限界を理解した上で、医師と相談しながら適切に活用することが大切です。
参考文献・出典情報
- 国立がん研究センター:リキッドバイオプシー活用でがんの克服目指す
- 国立がん研究センター:CIRCULATE-Japan GALAXY、リキッドバイオプシーによる大腸がんの再発リスクと術後治療効果の予測に有効性を確認
- National Cancer Institute:FDA Approves Blood Tests That Can Help Guide Cancer Treatment
- Grand View Research:Liquid Biopsy Market Size & Share Report 2030
- Market Report:世界のリキッドバイオプシー市場(2025年~2030年)
- The ASCO Post:The Evolution of Liquid Biopsy in Cancer Care
- 同友会メディカルニュース:リキッドバイオプシーの現状と未来
- ASCO Daily News:Clinical Applications of ctDNA in Colorectal Cancer
- Columbia University Irving Medical Center:What to Know About Liquid Biopsies for Cancer
- Illumina:リキッドバイオプシーのパワーと将来性



