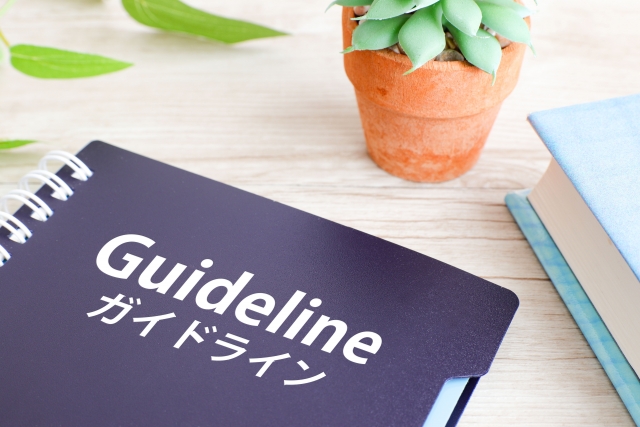
がん診療ガイドラインとは何か
がん診療ガイドラインとは、科学的根拠(エビデンス)に基づいて、現時点で最良と考えられる検査や治療法を提示する文書のことです。各専門学会が、患者さんと医療者の判断を支援する目的で作成しています。
がん治療を受ける際に「標準治療」という言葉を耳にすることがありますが、標準治療とは、多くの臨床試験の結果を専門家が検討し、有効性と安全性が確認された「最良の治療」を意味します。診療ガイドラインには、この標準治療に関する詳細な情報がまとめられています。
診療ガイドラインは主に医療者向けに書かれていますが、乳がん、胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、卵巣がんなどでは、医療者向けのガイドラインをもとにした「患者さんのためのガイドライン」や「患者さんのためのガイドブック」も作成されています。これらは一般の方向けに、わかりやすい文章や図で病気や治療について解説しています。
患者さんが把握しておくべき診療ガイドラインの基本
標準治療と診療ガイドラインの関係
診療ガイドラインに基づく治療が標準治療です。全国のがん診療連携拠点病院などでは、診療ガイドラインに沿った標準治療が行われています。ここで重要なのは、「最新の治療」が必ずしも「最良の治療」ではないという点です。
最新の治療が標準治療になるためには、それまでの標準治療より優れていることを証明する必要があります。そのため、臨床試験を通じて効果や副作用を調べることになります。つまり、新しいというだけでは最良とは言えないのです。
エビデンスレベルと推奨度の意味
診療ガイドラインを理解する上で知っておきたいのが、エビデンスレベルと推奨度という概念です。
エビデンスレベルとは、治療効果の推定値に対する確実さの程度を示すものです。多くのガイドラインでは、A(結果がほぼ確実)、B(結果を支持する研究はあるが十分ではない)、C(質の高い研究がない)の3段階で示されています。
推奨度は、その治療を実施することの推奨の強さを表します。一般的には「強く勧める」か「弱く勧める(条件付きで勧める)」の2種類で示されます。推奨度を決定する際には、治療の効果(益)と副作用などの害や負担のバランス、エビデンスの確実性、患者さんの価値観、費用対効果などが総合的に検討されます。
| エビデンスレベル | 意味 |
|---|---|
| A | 結果がほぼ確実で、今後新しい研究が行われても結果が大きく変化する可能性は少ない |
| B | 結果を支持する研究はあるが十分ではなく、今後の研究で結果が変化する可能性がある |
| C | 結果を支持する質の高い研究がない |
ガイドラインは絶対ではない
診療ガイドラインに書かれている内容は強制ではありません。がんの種類や進行の程度、体の状態、他の病気の有無などによって、ガイドラインで推奨されている治療を受けることが難しい場合もあります。
医師は診療ガイドラインを基本としながらも、一人ひとりの状況に応じて「その人にとっての最適な治療」を探ります。診療ガイドラインは、患者さんと医療者が一緒に治療方針を考えていくための「出発点」のようなものなのです。
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
患者さんが診療ガイドラインを活用するには
診療ガイドラインの入手方法
診療ガイドラインは、書店やインターネットで購入できます。書店にない場合は取り寄せも可能です。また、ガイドラインを作成した学会のホームページで無料公開されている場合もあります。
公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する「Mindsガイドラインライブラリ」では、日本で公開されているさまざまな疾患の診療ガイドラインが紹介されています。著作者から許諾が得られたガイドラインについては、内容も閲覧できます。
日本癌治療学会の「がん診療ガイドライン」サイトでは、脳腫瘍、肺がん、乳がん、胃がん、大腸がん、肝がん、膵がん、腎がん、前立腺がん、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんなど、臓器別のガイドラインにアクセスできます。2024年には肺癌診療ガイドライン2024年版、胆道癌診療ガイドライン、後腹膜肉腫ガイドライン、制吐薬適正使用ガイドラインなどが公開されました。また、2025年には頭頸部癌診療ガイドライン2025年版や胃癌治療ガイドライン第7版などが発行されています。
最新版を確認することの重要性
診療ガイドラインを活用する際には、必ず最新版を利用しましょう。医療は日々進歩しており、検査法や治療法のエビデンスも変化します。そのため、多くのガイドラインは3年から5年ごとに定期的に改訂されています。
特に、最新版であっても出版年が古いガイドラインに書かれている内容には注意が必要です。また、がんの種類によっては、治療に関連する臨床試験の最新結果などが「速報」として学会のウェブサイトで公開される場合もあります。最新の情報は主治医に確認することをお勧めします。
患者向けガイドラインの活用
医療者向けのガイドラインは専門用語が多く、一般の方には難しい内容も含まれています。そのため、まずは患者向けに作成されたガイドラインやガイドブックから読み始めるのがよいでしょう。
国立がん研究センターの「がん情報サービス」では、診療ガイドラインに基づいて、病気や検査、治療に関する概要を一般の方向けにわかりやすく掲載しています。こうした情報源も併せて活用すると、より理解が深まります。
診療ガイドライン活用時の注意点
自分のがんに該当する内容を見極める
診療ガイドラインには多くの情報が含まれていますが、すべてが自分の状況に当てはまるわけではありません。がんの種類、ステージ、年齢、体の状態、他の病気の有無などによって、適切な治療は異なります。
ガイドラインを読む際には、自分のがんの病期や病理診断の結果など、正確な情報をもとに該当する部分を確認することが大切です。わからない点や疑問点は、主治医に相談しましょう。
医師とのコミュニケーションに活用する
診療ガイドラインは、患者さんと医療者が治療方針を一緒に考えるためのツールです。ガイドラインを読んで疑問に思ったこと、自分の治療との違いなどを主治医に質問することで、より良い意思決定につながります。
「一人ひとりにとっての最適な治療」の選択においては、がんの治療だけでなく、治療が始まってからの生活のことも含めて、その人が何を大切にしたいかがポイントになります。診療ガイドラインの情報を踏まえながら、自分の価値観や希望を医療者に伝えることが重要です。
希少がんの場合の対応
患者数が少ない希少がんなどでは、診療ガイドラインや標準治療が確立されていないことがあります。このような場合、主治医は関連する他のがん種のガイドラインや、海外のガイドライン、最新の論文などを参考にしながら治療方針を検討します。
希少がんの診療では、専門的な知識や経験を持つ医療機関や医師に相談することも選択肢の一つです。
2025年の診療ガイドライン動向
2025年には、さまざまながん診療ガイドラインの改訂や新規発行が予定されています。肺癌診療ガイドラインは2024年版が2025年6月にバージョン1.1として更新され、小細胞肺癌の項目に新たなクリニカルクエスチョンが追加されました。また、頭頸部癌診療ガイドライン2025年版が2025年5月に発行されるなど、各学会が最新のエビデンスに基づく情報更新を進めています。
患者さんとしては、自分のがん種に関連するガイドラインが更新された際には、新しい治療選択肢や推奨内容の変更について、主治医と話し合う機会を持つことをお勧めします。
アドバイス
診療ガイドラインは確かに重要な情報源ですが、それだけで治療を決めるものではないということです。
ガイドラインに記載された標準治療は、多くの患者さんにとって最良の選択肢ですが、一人ひとりの状況は異なります。体力、年齢、価値観、生活状況、家族構成など、さまざまな要素が治療選択に影響します。
診療ガイドラインを理解した上で、自分の状況や希望を医療者にしっかり伝え、一緒に治療方針を考えていくことが、納得のいく治療につながります。医師に質問することをためらわず、わからないことは何度でも聞くことが大切です。
診療ガイドラインに関する情報源
診療ガイドラインについてさらに詳しく知りたい場合、以下のような情報源が役立ちます。
Mindsガイドラインライブラリでは、診療ガイドラインの定義や重要用語の基礎知識、患者・市民向けのQ&Aなども公開されています。また、各がん種の学会ホームページでは、最新のガイドライン情報や、治療に関する速報が掲載されることがあります。
国立がん研究センターのがん情報サービスは、信頼性の高い情報を一般の方向けにわかりやすく提供しており、診療ガイドラインの概要や活用方法についても詳しく解説しています。
参考文献・出典情報
- 国立がん研究センター がん情報サービス「標準治療と診療ガイドライン」
- 日本癌治療学会「がん診療ガイドライン」
- 公益財団法人日本医療機能評価機構「Mindsガイドラインライブラリ」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「診療ガイドラインを理解し活用するための基礎知識」
- 日本肺癌学会「肺癌診療ガイドライン2024年版」
- 日本胃癌学会「ガイドライン」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「各種ガイドライン等の情報へのリンク集」
- 日本癌治療学会「がん疼痛薬物療法ガイドライン 推奨の強さとエビデンスレベル」
- 金原出版「シリーズ:診療ガイドラインの書籍一覧」
- 日本医療機能評価機構「患者さんのための胃がん治療ガイドライン 2023年版」



