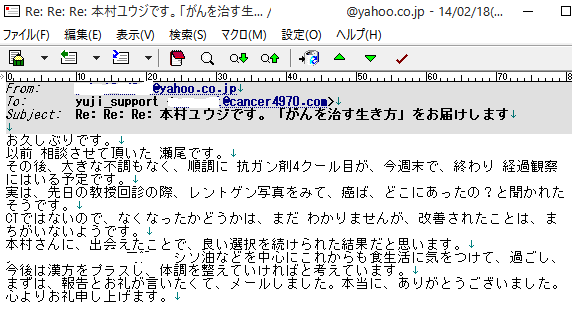【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
腫瘍減量手術(デバルキング)とは何か
腫瘍減量手術(デバルキング・サージャリー)は、がんの完全な切除が困難な場合に、可能な限り腫瘍の量を減らすことを目的として行われる手術です。
通常の根治手術では、がん組織をすべて取り除くことが目標となりますが、腫瘍減量手術では、原発巣や転移巣の一部が残存することを前提としています。この手術は、根治目的の手術後に切除断端が陽性となる状況とは明確に区別される必要があります。
腫瘍減量手術が効果を発揮するためには、全体の腫瘍量に対して十分な量の腫瘍を切除することが重要です。切除可能な腫瘍量が不十分な場合、期待される治療効果が得られない可能性があるため、手術前の慎重な評価が必要となります。
腫瘍減量手術の基本的な考え方
腫瘍減量手術は、腫瘍の「塊」または主要部分を除去することで、患者さんの症状緩和や生存期間の延長を図る治療法です。特に進行がんにおいては、腫瘍量を減らすことで、その後の化学療法や放射線治療の効果を高めることが期待されます。
この手術の背景には、腫瘍量の減少により残存するがん細胞の他の治療法に対する感受性が向上するという考えがあります。ただし、その詳しい機序については、まだ完全には解明されていません。
腫瘍減量手術の種類と分類
実施時期による分類
腫瘍減量手術は、実施する時期によって以下の3種類に分類されます。
1. PDS(プライマリー・デバルキング・サージャリー)
初回治療として最初に行われる腫瘍減量手術です。がんの診断確定後、化学療法を開始する前に実施されます。手術時間が長く、出血量も多い傾向があり、合併症のリスクも高くなりますが、がんの広がりを直接確認しながら可能な限りの腫瘍切除を行うことができます。
2. IDS(インターバル・デバルキング・サージャリー)
初回化学療法の途中段階で行われる腫瘍減量手術です。まず数回の化学療法で腫瘍を縮小させてから手術を実施するため、PDSと比較して手術時間が短く、合併症のリスクも低くなる傾向があります。近年、このアプローチの有効性が注目されています。
3. SDS(セカンダリ・デバルキング・サージャリー)
初回治療終了後にがんが残存している場合や、再発した場合に行われる腫瘍減量手術です。患者さんの全身状態や腫瘍の状況を総合的に判断して実施されます。
残存腫瘍の程度による分類
2025年の最新の医学文献によると、腫瘍減量手術は残存腫瘍の程度によって以下の3つのタイプに分類されています。
| タイプ | 原発巣の状態 | 転移巣の状態 |
|---|---|---|
| タイプ1 | 完全切除 | 切除不能な転移巣が残存 |
| タイプ2 | 不完全切除 | 転移巣なし |
| タイプ3 | 不完全切除 | 切除不能な転移巣が残存 |
がんの種類によって目的とするデバルキング手術のタイプが異なり、残存腫瘍に対する追加治療を検討する際には、どのタイプの手術が行われたかを把握することが重要です。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
腫瘍減量手術の適応となるがん種
卵巣がん
腫瘍減量手術が最も頻繁に行われ、その有効性が確立されているがん種です。特に進行期(III期・IV期)の卵巣がんでは、標準的な治療法として位置づけられています。2021年の研究では、再発卵巣がんに対する腫瘍減量手術により、化学療法のみの治療と比較して全生存期間が約16カ月延長することが報告されています。
卵巣がんの場合、手術で残存腫瘍径を1cm以下にする「オプティマル手術」の達成率が治療成績に大きく影響することが知られています。米国の専門施設では、進行卵巣がんに対してオプティマル手術の割合が70~80%に達しており、これが良好な治療成績につながっています。
副腎腫瘍
褐色細胞腫やパラガングリオーマ、副腎皮質がんなどの副腎腫瘍に対しても、腫瘍減量手術の有効性が報告されています。特に転移性の褐色細胞腫では、カテコラミン過剰状態を抑制することで循環動態の安定化とQOL向上に寄与することが期待されます。
2025年の最新報告では、転移性褐色細胞腫患者の56%で術後にカテコラミンが基準値範囲内にコントロールできたという結果が示されています。
腎細胞がん
有転移症例でも原発巣を摘除するcytoreductive nephrectomyが行われることがあります。ただし、免疫チェックポイント阻害剤などの新しい治療薬の登場により、その適応や有効性の解釈が変化してきており、現在も臨床試験が進行中です。
大腸がん
腹膜播種を伴う大腸がんに対して、腫瘍減量手術と腹腔内温熱化学療法(HIPEC)を組み合わせた治療が海外では報告されています。ただし、実施できる医療機関は限られており、日本ではまだ一般的な治療法ではありません。
その他のがん種
胃がん、乳がん、前立腺がんなどでも、特定の状況下で腫瘍減量手術が検討される場合があります。基本的に増殖速度が比較的遅い腫瘍がその適応になると考えられています。
腫瘍減量手術の適応基準
手術適応の基本的な考え方
腫瘍減量手術の適応を決定する際には、以下の要素を総合的に評価する必要があります。
患者さんの全身状態が手術に耐えられること、切除可能な腫瘍量が十分であること、術後の化学療法や放射線治療が可能であることなどが重要な判断基準となります。また、症状緩和や生存期間延長の見込みがあることも必要な条件です。
適応となる条件
手術で除去できる目に見える腫瘍が存在すること、腹痛や腸閉塞など腫瘍量に関連する症状があること、以前の化学療法後も残存病変があることなどが適応となる条件として挙げられます。
一方で、手術に耐えられない全身状態の患者さん、切除可能な腫瘍量が不十分な場合、多臓器不全のリスクが高い場合などは適応外となります。
施設と医師の要件
腫瘍減量手術は高度な技術と経験を要する手術であるため、十分な症例数と実績を有する医療施設で実施されることが推奨されます。また、外科医、腫瘍内科医、放射線科医、病理医などの多職種チームによる集学的治療が重要です。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
腫瘍減量手術の効果と治療成績
生存期間への影響
2021年に発表されたDESKTOP III試験では、再発卵巣がんに対する腫瘍減量手術により、化学療法のみの治療と比較して全生存期間が延長することが前向きランダム化比較試験で初めて証明されました。この結果は、腫瘍減量手術の有効性を示す重要なエビデンスとなっています。
副腎腫瘍の分野では、転移性褐色細胞腫113例の解析において、原発巣摘除群は非摘除群と比較して有意に生存期間が長いことが示されています。
症状緩和効果
腫瘍減量手術は、腫瘍による圧迫症状や閉塞症状の緩和にも効果があります。特に消化管の閉塞や疼痛の軽減により、患者さんのQOLが改善することが期待されます。
カテコラミン産生腫瘍である褐色細胞腫では、腫瘍量を減らすことでカテコラミン過剰状態を抑制し、循環動態の安定化を図ることができます。
後続治療への影響
腫瘍量を減らすことで、その後の化学療法や放射線治療の効果が向上することが期待されます。腫瘍減量手術により、残存するがん細胞の治療薬に対する感受性が高まる可能性があります。
腫瘍減量手術のリスクと限界
手術に伴うリスク
腫瘍減量手術は通常の手術よりも大がかりになることが多く、手術時間の延長、出血量の増加、合併症のリスクが高くなる傾向があります。特にPDSでは、手術に関連した死亡のリスクも存在します。
術後の合併症として、感染症、縫合不全、腸閉塞などが起こる可能性があります。また、多臓器にわたる手術を行う場合には、臓器機能の低下や術後の回復遅延が生じることもあります。
効果の限界
現在のところ、腫瘍減量手術を行った場合と行わなかった場合を比較する大規模なランダム化比較試験のデータが限られているため、すべてのがん種で生存期間延長効果が証明されているわけではありません。
また、手術で除去できる腫瘍量が不十分な場合には、期待される治療効果が得られない可能性があります。このため、術前の画像診断による切除可能性の評価が重要となります。
患者さんの負担
大がかりな手術となることが多いため、患者さんの身体的負担も相当なものとなります。術後の回復に時間がかかり、その間は化学療法の開始が遅れる可能性もあります。
腫瘍減量手術の将来展望
技術的進歩
ロボット支援手術や腹腔鏡下手術などの低侵襲手術技術の発達により、従来よりも患者さんの負担を軽減しながら腫瘍減量手術を行うことが可能になってきています。2024年には国立がん研究センターで最新の手術支援ロボット「ダビンチSP」が導入されるなど、技術革新が続いています。
個別化医療の進展
遺伝子解析技術の進歩により、患者さん一人ひとりのがんの特性に応じた治療選択が可能になってきています。腫瘍減量手術の適応についても、より精密な予測が可能になることが期待されます。
集学的治療の発展
免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬などの新しい治療薬の登場により、腫瘍減量手術と薬物療法を組み合わせた集学的治療の可能性が広がっています。治療選択肢の増加により、より多くの患者さんが恩恵を受けることが期待されます。
患者さんとご家族が知っておくべきこと
十分な説明と相談
腫瘍減量手術は、すべてのがん患者さんに適用される治療法ではありません。がんの種類、進行度、患者さんの全身状態、他の治療選択肢との比較など、様々な要素を総合的に検討する必要があります。
担当医から手術の目的、期待される効果、リスク、代替治療法について十分な説明を受け、納得したうえで治療方針を決定することが重要です。
セカンドオピニオンの活用
腫瘍減量手術は専門性の高い治療であるため、必要に応じて他の専門医の意見を求めることも大切です。複数の医師の見解を聞くことで、より適切な治療選択ができる可能性があります。
術後のフォローアップ
腫瘍減量手術後は、定期的な検査により再発や転移の有無を確認する必要があります。また、術後の化学療法や放射線治療についても、計画的に実施することが重要です。
まとめ
腫瘍減量手術(デバルキング)は、根治的な切除が困難な進行がんに対する重要な治療選択肢です。特に卵巣がんでは標準的な治療法として確立されており、その他のがん種でも症例に応じて検討される治療法となっています。
2025年の最新知見では、適切に選択された患者さんに対して実施される腫瘍減量手術は、症状緩和や生存期間延長に寄与する可能性があることが示されています。ただし、手術に伴うリスクも存在するため、患者さんの状態やがんの特性を総合的に評価したうえで、適応を慎重に判断する必要があります。
参考文献・出典情報
- 副腎腫瘍のデバルキング手術 - 日本内分泌外科学会雑誌 2025年42巻1号
- 腫瘍減量手術 - がん治療の情報サイト
- 再発卵巣癌に対する腫瘍減量手術の無作為化試験 - The New England Journal of Medicine日本版
- 卵巣がんの治療について - がんの先進医療
- 手術支援ロボット「ダビンチSP」を用いたがん手術を実施 - 国立がん研究センター
- 大腸癌治療ガイドライン - 大腸癌研究会
- 卵巣がん治療ガイドライン - 日本癌治療学会
- がんに対する手術 - MSDマニュアル プロフェッショナル版
- 再発卵巣がんに対する腫瘍減量手術は完全切除で化学療法群と比較してOSを16カ月延長 - 日経バイオテクONLINE
- 細胞減量手術 - アポロ病院
本記事の情報は2025年8月時点のものです。がん治療に関する決定は、必ず担当医と十分に相談のうえ行ってください。