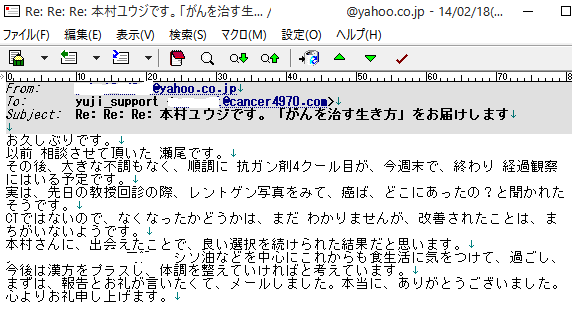【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
がん手術におけるR0・R1・R2切除の基礎知識
がん手術を行う際に最も重要な評価項目の一つが、手術による腫瘍の切除がどれだけ完全に行われたかという「根治性」です。この根治性を客観的に評価するために用いられるのが、R0・R1・R2切除という分類システムです。
R分類は「Residual Tumor」(遺残腫瘍)の略で、手術後に腫瘍がどの程度残存しているかを示す国際的な評価基準です。1987年に国際対がん連合(UICC)によって採用されたこの分類は、がん治療の効果を評価し、今後の治療方針を決定する上で欠かせない指標となっています。
R0切除(完全切除)の定義と意味
R0切除とは、手術において肉眼的にも顕微鏡的にも腫瘍が完全に切除された状態を指します。別名「完全切除」や「治癒切除」とも呼ばれます。
R0切除と判定されるためには、以下の条件が満たされる必要があります:
- 肉眼的に腫瘍が完全に切除されている
- 病理検査で切除断端に腫瘍細胞が認められない
- 遠隔転移がない状態
手術で摘出された組織は病理医によって詳細に検査され、切除された断端のすべてが顕微鏡で確認されます。その結果、どの断端にも腫瘍細胞が認められなかった場合にR0切除と判定されます。
ただし、R0切除(治癒切除)といっても、切除した時点で完全に治癒したという意味ではないことに注意が必要です。微小な転移や循環腫瘍細胞が存在する可能性があるため、術後の定期的な経過観察が重要になります。
R1切除(顕微鏡的不完全切除)の詳細
R1切除は、肉眼的には腫瘍を完全に切除したものの、顕微鏡検査で切除断端に腫瘍が残っている状態を指します。外科医の目には腫瘍が完全に取り切れたように見えても、病理検査で初めて腫瘍の遺残が判明するケースです。
R1切除となる主な状況:
- 切除断端に腫瘍細胞が付着している
- 安全域(サージカルマージン)が不十分
- 腫瘍の浸潤が予想以上に広範囲であった
R1切除の患者さんに対しては、遺残が疑われる臓器を標的とした綿密なサーベイランスを計画する必要があります。また、症例によっては追加の手術や放射線治療、化学療法が検討されます。
R2切除(肉眼的不完全切除)について
R2切除は、手術において肉眼的に明らかに腫瘍が取り切れなかった状態を指します。手術中に外科医が腫瘍の一部を意図的に残さざるを得なかった、または技術的な理由で完全切除が困難だった場合に該当します。
R2切除となる状況:
- 腫瘍が重要な臓器に浸潤し、完全切除が生命に危険を及ぼす場合
- 技術的に切除不可能な部位に腫瘍が存在する場合
- 患者さんの全身状態により手術時間の延長が困難な場合
R2切除の場合、根治的な治療効果は期待できないため、症状の緩和や腫瘍量の減少(デバルキング)を目的とした姑息的手術として位置づけられることが多くなります。
R分類が患者さんの予後に与える影響
R分類は治療効果を反映し、今後の治療計画に影響を与える強力な予後予測因子として確立されています。各分類によって予後は明確に異なることが多くの研究で示されています。
R0切除の予後
R0切除を達成した患者さんは最も良好な予後が期待できます。長期的な良好な予後はR0患者でのみ期待できるとされており、多くのがん種において5年生存率が最も高くなります。
ただし、R0切除を達成したとしても、がんの進行度(ステージ)や組織型、患者さんの年齢や全身状態によって予後は変わることに注意が必要です。
R1・R2切除の予後への影響
R1切除とR2切除はともに不完全切除と分類され、R0切除と比較して予後が不良になる傾向があります。しかし、R分類による予後の違いは、ステージの違いだけでは説明できない独立した予後因子であることが知られています。
R1切除の場合、追加治療により予後の改善が期待できることもあります。一方、R2切除の場合は根治的な治療効果は困難ですが、症状緩和や生活の質の向上に寄与することがあります。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
病理検査における切除断端の評価方法
R分類の正確な判定には、切除断端の病理学的検査が信頼性のある分類を行うために必要です。病理医は摘出された組織を詳細に検査し、以下の評価を行います。
病理検査の手順
摘出された組織は病理検査室に送られ、以下の手順で評価されます:
- 肉眼的観察による腫瘍の確認
- 組織の固定と薄切標本の作成
- 顕微鏡による切除断端の詳細な検査
- 免疫組織化学的検査(必要に応じて)
サージカルマージンの重要性
がん手術においては、腫瘍から一定の距離を保って切除する「サージカルマージン」(安全域)の確保が重要です。このマージンが十分であれば、微小な腫瘍の浸潤があっても完全切除が可能になります。
適切なサージカルマージンの距離は、がんの種類や部位によって異なります。例えば、乳がんの場合は通常1-2mm以上、消化器がんでは数センチメートルの安全域が推奨されることがあります。
R分類に基づく治療戦略の立案
R分類の結果は、術後の治療方針を決定する重要な要素となります。患者さんの治療計画は、この分類結果を踏まえて個別に立案されます。
R0切除後の管理
R0切除を達成した患者さんに対しては、以下の管理が行われます:
- 定期的な画像検査による再発監視
- 腫瘍マーカーの測定
- 必要に応じた術後補助療法の実施
R0切除が行われたStage III大腸がんに対しては、再発抑制と予後改善を目的とした術後補助化学療法が標準的に実施されます。
R1切除後の対応
R1切除の場合は、以下の治療選択肢が検討されます:
- 追加手術(再切除)
- 放射線治療
- 化学療法の強化
- 集学的治療の組み合わせ
治療方針は、患者さんの全身状態、がんの種類や進行度、初回手術からの経過時間などを総合的に考慮して決定されます。
R2切除後の管理
R2切除の場合は、根治よりも症状緩和と生活の質の維持が主な目標となります:
- 残存腫瘍に対する放射線治療
- 全身化学療法
- 症状緩和のための支持療法
- 疼痛管理
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
がん種別のR分類の特徴
R分類の意味や予後への影響は、がんの種類によって異なる特徴があります。主要ながん種における特徴を説明します。
大腸がんにおけるR分類
大腸がんにおいては、R0切除率97.0%、縫合不全発生率9.1%、局所再発率6.7%という良好な成績が報告されています。大腸がんは比較的R0切除を達成しやすいがん種の一つです。
直腸がんの場合、周囲切除断端(CRM:Circumferential Resection Margin)の評価が特に重要で、腫瘍と周囲切除断端の最短距離が1mm以下の場合はCRM陽性と判定されます。
肺がんにおける特殊性
肺がんにおいては、従来のR分類に加えて、残存腫瘍の存在が不確実な状況を含む追加カテゴリーが設けられています。これは肺がん特有の解剖学的特徴と手術の複雑さを反映しています。
肺がん手術では、リンパ節郭清の適切性や胸膜浸潤の有無なども R分類の判定に影響を与える重要な要素となります。
肝がんの切除における課題
肝細胞がんの切除では、R0切除が87.5%、R1切除が4.2%、R2切除が8.3%という報告があります。肝がんは血管が豊富で手術の難易度が高く、完全切除の達成が技術的に困難な場合があります。
R分類の限界と今後の展望
R分類は非常に有用な評価システムですが、いくつかの限界も指摘されています。
現在の課題
- 病理検査の技術や判定基準に施設間差がある
- 微小転移の検出限界
- 循環腫瘍細胞の評価が含まれていない
- 分子生物学的マーカーとの関連性
新しい評価方法の導入
R分類の新しい手法として、捺印細胞診、腹水の細胞学的検査、骨髄生検の検査などが研究されています。これらの技術により、従来の病理検査では検出できなかった微小な腫瘍細胞の検出が可能になる可能性があります。
患者さんが知っておくべきポイント
がん手術を受ける患者さんとご家族にとって、R分類の理解は治療への理解を深める上で重要です。
手術前の準備
- 手術の目標(R0切除の可能性)について主治医と十分に話し合う
- 手術のリスクと利益を理解する
- 術後の治療計画について確認する
手術後の対応
- 病理結果の説明を受ける際はR分類について質問する
- R分類に基づく今後の治療方針を確認する
- 定期的な経過観察の重要性を理解する
R分類結果の受け止め方
R0切除を達成できなかった場合でも、決して治療の失敗を意味するものではありません。R1やR2切除でも、追加治療により良好な結果が得られることがあります。重要なのは、R分類の結果を踏まえて最適な治療を継続することです。
まとめ
R0・R1・R2切除の分類は、がん手術の成果を客観的に評価し、患者さんの予後を予測する重要な指標です。R0切除の達成は最も良好な予後が期待できますが、R1やR2切除でも適切な追加治療により改善が期待できる場合があります。
参考文献・出典情報
- がん情報サイト「オンコロ」- R0切除について
- 大腸癌研究会 - 大腸癌治療ガイドライン
- Cancer Journal - TNM residual tumor classification revisited
- ScienceDirect - The Pathologist and the Residual Tumor Classification
- PubMed - Residual tumor classification and prognosis
- Radiopaedia - Residual tumor classification
- Cancer Journal - A uniform residual tumor classification
- Journal of Thoracic Oncology - Lung Cancer Staging Project
- 日経メディカル - 肝細胞癌コンバージョン手術の報告
- Medical Education - オンコロジー入門