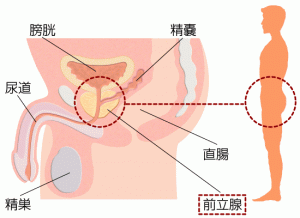
こんにちは。がん専門のアドバイザー、本村ユウジです。
前立腺がんの治療において、放射線治療は手術療法と並ぶ根治を目指せる重要な選択肢です。近年の技術進歩により、放射線治療の精度と効果は大きく向上しています。
この記事では、前立腺がんの放射線治療について、どのような患者さんが対象になるのか、どのような種類の治療法があるのか、使用される放射線量、期待できる効果、そして起こりうる後遺症について詳しく解説します。
前立腺がんに対する放射線治療の基本的な考え方
前立腺がんの放射線治療は、高エネルギーの放射線をがん細胞に照射することで、DNA を損傷させて細胞の増殖能力を失わせる治療法です。
放射線治療の最大の特徴は、手術療法と比較して治療成績がほぼ同等でありながら、患者さんの生活の質(QOL)を維持しやすい点にあります。
手術療法では、勃起機能障害や尿失禁といった副作用が高い頻度で発生します。一方、放射線治療では、こうした副作用の発生率が比較的低く抑えられています。ただし、放射線治療には直腸障害や膀胱障害といった特有の副作用があることも理解しておく必要があります。
放射線治療の適応条件とリスク分類
前立腺がんの放射線治療を選択する際、最も重要なのはリスク分類による適応判断です。前立腺がんの治療成績は病期分類だけでなく、複数のリスク因子によって大きく左右されます。
リスク分類の基準
前立腺がんのリスク分類は、PSA値(腫瘍マーカー)、グリソンスコア(病理組織分類)、臨床病期の3つの要素を組み合わせて行われます。
| リスク分類 | PSA値(ng/mL) | グリソンスコア | 臨床病期 |
|---|---|---|---|
| 低リスク群 | 10以下 | 6以下 | T1c~T2a |
| 中リスク群 | 10超~20以下 | 7 | T2b |
| 高リスク群 | 20超 | 8以上 | T2c~T3 |
このリスク分類によって、放射線治療単独で治療を行うか、ホルモン療法を併用するかが決定されます。
リスク分類別の治療方針
低リスク群の前立腺がんでは、放射線治療単独で十分な効果が期待できます。この段階のがんは前立腺内にとどまっており、周辺組織への浸潤やリンパ節転移がほとんど認められません。
中リスク群では、放射線治療とホルモン療法の併用が検討されることがあります。中リスク群では前立腺被膜への浸潤が認められることがあり、放射線治療の効果を高めるためにホルモン療法を組み合わせる場合があります。併用期間は一般的に6か月程度です。
高リスク群では、放射線治療とホルモン療法の併用が強く推奨されています。リスクが高くなるにつれて前立腺周囲への浸潤やリンパ節転移の頻度が増加するため、局所治療である放射線療法に加えて全身療法であるホルモン療法を組み合わせることで、より高い治療効果が得られます。併用期間は2~3年程度が標準的です。
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
放射線治療の種類と特徴
前立腺がんの放射線治療には、大きく分けて外部照射法と組織内照射法(小線源療法、ブラキセラピー)の2種類があります。それぞれに特徴があり、患者さんの状態や希望に応じて選択されます。
外部照射法の種類と照射方法
外部照射法は、体の外から放射線を照射する治療法です。前立腺がんの外部照射では、主に10メガボルト(MV)のX線が使用されます。
従来は120度振子照射法や4門照射法が一般的でしたが、現在では3次元原体照射法(3D-CRT)や強度変調放射線治療(IMRT)といった高精度の照射技術が広く用いられるようになっています。
3D-CRTは、CT画像をもとに前立腺の形状を3次元的に把握し、照射範囲を腫瘍の形に合わせて設定する方法です。照射野は一般的に6センチメートル×6センチメートル、あるいは8センチメートル×8センチメートルで設定されます。
IMRTは、3D-CRTをさらに進化させた技術で、照射範囲内で放射線の強度を細かく調整できます。これにより、前立腺には高い線量を集中させながら、周囲の直腸や膀胱への照射量を最小限に抑えることが可能になります。
外部照射で使用される放射線量
外部照射では、1回あたりの線量を1.8~2グレイに設定し、週5回(月曜日から金曜日まで)のペースで照射を続けます。
骨盤部全体への総線量は45~50グレイが標準的です。前立腺本体に対しては、さらに追加照射を行い、総線量で65~76グレイを照射します。
治療期間は照射する総線量によって異なりますが、一般的には7~8週間程度です。外来通院で治療を受けることができるため、入院の必要はありません。
ただし、70グレイを超える高線量を照射する場合には、重篤な直腸障害が高い頻度で発生することが知られています。そのため、現在では精密な照射技術を用いることで、直腸への線量を抑えながら前立腺には十分な線量を照射する工夫が行われています。
組織内照射法(小線源療法)の特徴
組織内照射法は、前立腺の中に直接、放射線を放出する小さなカプセル(シード)を埋め込む治療法です。ブラキセラピーとも呼ばれます。
前立腺がんの組織内照射では、ヨウ素125(I-125)という放射性同位元素を封入したシードが使用されます。シードは米粒より小さな金属製のカプセルで、長さ約4.5ミリメートル、直径約0.8ミリメートルです。
治療は、超音波ガイド下で経会陰的に前立腺内にシードを刺入します。シードの数は前立腺の大きさによって異なりますが、一般的には60~100個程度が埋め込まれます。
シードは永久刺入型であり、一度埋め込むと取り出すことはありません。ヨウ素125の半減期は約60日で、約1年かけて放射線を放出し続けます。その後は放射能がほぼなくなるため、人体への影響はありません。
組織内照射法の大きな利点は、入院期間が短いことです。通常1~3日の入院で治療が完了します。また、前立腺内部から高線量を照射できるため、周囲の正常組織への影響を最小限に抑えられます。
組織内照射法の適応条件
組織内照射法が適応となるのは、主に低リスク群および一部の中リスク群の患者さんです。以下の条件を満たす必要があります。
- PSA値が10 ng/mL以下(施設によっては20 ng/mL以下)
- グリソンスコアが7以下
- 臨床病期がT1~T2a(施設によってはT2b)
- 前立腺の体積が50 cc以下(大きすぎるとシードの配置が困難)
- 重度の排尿障害がないこと
- 過去に前立腺の手術歴がないこと
前立腺が大きい場合には、事前にホルモン療法で前立腺を縮小させてから組織内照射を行うこともあります。
放射線治療の効果と治療成績
前立腺がんの放射線治療の効果は、PSA非再発率という指標で評価されます。これは、治療後にPSA値が一定の基準以下に維持されている患者さんの割合を示すものです。
外部照射単独療法の治療成績
外部照射で70グレイを照射した場合の10年PSA非再発率は、リスク分類によって以下のように報告されています。
| リスク分類 | 10年PSA非再発率 |
|---|---|
| 低リスク群 | 約80% |
| 中リスク群 | 約50% |
| 高リスク群 | 約30% |
より高い線量(76~80グレイ)を照射することで、治療成績の向上が期待できます。IMRTなどの高精度照射技術を用いることで、副作用を抑えながら高線量照射が可能になっています。
ホルモン療法併用時の治療成績
中リスク群および高リスク群では、放射線治療にホルモン療法を併用することで、PSA非再発率が向上することが複数の臨床試験で示されています。
高リスク群において、放射線治療単独と放射線治療+ホルモン療法(2~3年間)を比較した研究では、併用群の10年PSA非再発率が単独群より15~20%程度高くなることが報告されています。
組織内照射法の治療成績
組織内照射法単独での10年PSA非再発率は、低リスク群で85~90%と良好な成績が報告されています。中リスク群では、組織内照射と外部照射を併用することもあります。
放射線治療の副作用と後遺症
放射線治療には、治療中に現れる急性期の副作用と、治療後しばらくしてから現れる晩期障害(後遺症)があります。
急性期の副作用
急性期の副作用は、治療開始後2~3週間頃から現れ始めます。主な症状としては以下のものがあります。
排尿に関する症状では、頻尿、排尿時痛、残尿感、夜間頻尿などが認められます。これらは膀胱が放射線の影響を受けることで生じる放射線性膀胱炎の症状です。症状の程度は個人差がありますが、多くの患者さんで何らかの排尿症状が出現します。
消化器系の症状では、下痢、軟便、腹部不快感などが現れることがあります。これは直腸が放射線の影響を受けることで生じます。頻度は排尿症状より低いですが、日常生活に影響する場合があります。
その他、肛門周囲の皮膚炎や直腸出血が認められることもあります。皮膚炎は照射野に含まれる皮膚が反応して起こるもので、軽度のやけどのような状態になります。
これらの急性期副作用の多くは、治療終了後1~3か月程度で徐々に改善していきます。症状に対しては、薬物療法で対処することができます。
晩期障害(後遺症)
晩期障害は、治療終了後3か月以降に出現する副作用で、一度発生すると長期間持続する可能性があります。
最も注意が必要なのは放射線性直腸炎です。直腸出血として現れることが多く、便に血が混じったり、トイレットペーパーに血液が付着したりします。軽度であれば経過観察で済みますが、出血が多い場合には内視鏡的な止血処置が必要になることもあります。
発生頻度は照射線量や照射技術によって異なりますが、従来の照射法では10~15%程度、IMRTなどの高精度照射では5%以下に抑えられているとされています。
その他の晩期障害としては、慢性的な頻尿、尿意切迫感、勃起機能障害などがあります。勃起機能障害の発生率は手術療法より低いですが、治療前と比較すると機能低下が認められることがあります。
副作用を軽減するための工夫
現在の放射線治療では、副作用を軽減するために様々な工夫が行われています。
IMRTや画像誘導放射線治療(IGRT)といった高精度照射技術を用いることで、前立腺には十分な線量を照射しながら、直腸や膀胱への照射量を最小限に抑えることができます。
また、治療前のCT撮影時や毎回の治療時に、直腸内のガスや便の状態を確認し、できるだけ同じ条件で治療を行うことで、照射位置の再現性を高めています。
一部の施設では、直腸と前立腺の間にスペーサー(間隔保持材)を挿入することで、直腸への線量をさらに低減する試みも行われています。
放射線治療を受ける際の注意点
放射線治療を受けることが決まった場合、治療の効果を高め、副作用を最小限に抑えるために、いくつかの注意点があります。
治療前の準備
治療計画を立てるために、CT撮影やMRI撮影が行われます。この際、前立腺の位置を正確に特定するために、直腸内にマーカーを挿入したり、膀胱に一定量の尿を溜めた状態で撮影したりすることがあります。
また、前立腺内に金属製のマーカー(金粒子)を埋め込むこともあります。これにより、毎回の治療時に前立腺の位置を正確に確認できるようになります。
治療中の生活
治療期間中は、できるだけ毎回同じ条件で治療を受けることが重要です。排便や排尿の状態を一定に保つことで、照射位置の再現性が高まります。
具体的には、治療の1~2時間前に排便を済ませておくこと、治療前に一定量の水を飲んで膀胱に尿を溜めることなどが推奨されます。
食事については特別な制限はありませんが、下痢や便秘を防ぐために、バランスの良い食事を心がけることが大切です。辛い食べ物やアルコールの過度な摂取は、直腸への刺激となるため控えめにすることが望ましいとされています。
治療後の経過観察
治療終了後は、定期的な経過観察が必要です。PSA値の測定と診察を、最初の1年は3か月ごと、その後は半年ごとに行うことが一般的です。
PSA値は治療直後から低下し始めますが、最低値に達するまでには1~2年程度かかることがあります。治療後にPSA値が一時的に上昇する「PSAバウンス」という現象が起こることもありますが、これは必ずしも再発を意味するものではありません。
治療選択を考える際のポイント
前立腺がんの治療法を選択する際には、がんの進行度やリスク分類だけでなく、患者さん自身の年齢、全身状態、価値観なども重要な判断材料となります。
放射線治療は、手術療法と比較して以下のような特徴があります。
メリットとしては、入院が不要で外来通院で治療を受けられること、手術による合併症のリスクがないこと、尿失禁の発生率が低いこと、性機能の温存率が比較的高いことなどが挙げられます。
一方、デメリットとしては、治療期間が長くなること(7~8週間の通院が必要)、直腸障害のリスクがあること、治療効果の判定に時間がかかること(PSAの低下に時間を要する)などがあります。
また、再発した場合の救済治療として手術を行うことは技術的に困難な場合が多く、ホルモン療法などの他の治療法を選択することになります。
これらの特徴を理解した上で、自分に最も適した治療法を選択することが大切です。



